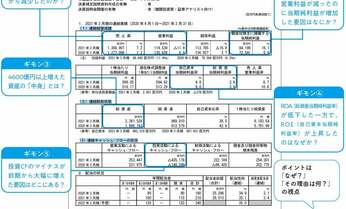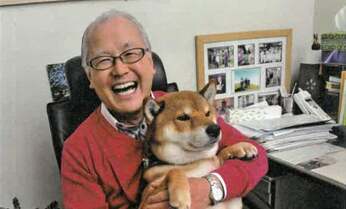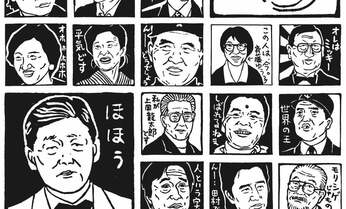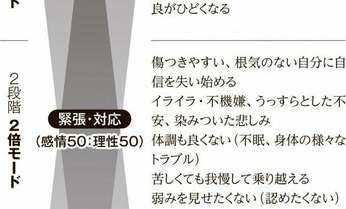
「読書」に関する記事一覧
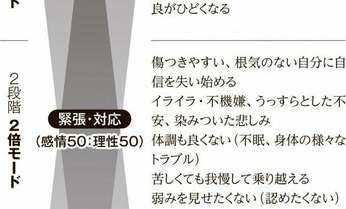



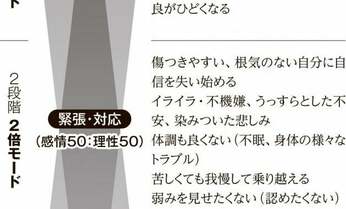

特集special feature

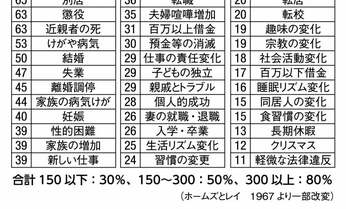

東電は「犠牲者を2度殺そうとしている」 東日本大震災から5年9カ月後に起きた“奇跡”と同じ場所で繰り返される“罪”の重さ
原発と基地――「国益」の名の下に犠牲を強いられる「苦渋の地」で今、何が起きているのか。政府や行政といった、権力を監視する役割を担うメディアは、その機能を果たせているのか。福島と沖縄を持ち場とする2人の新聞記者が、取材現場での出来事を綴った『フェンスとバリケード』。福島第一原発事故により帰宅困難区域に指定された福島県大熊町で見つかった子どもの遺骨……。著者で沖縄タイムスの阿部岳記者が取材した福島が今も直面している現実について綴った第14章「呼び合う者たち」から一部抜粋してお届けします。