
BOOKSTAND


膨大な資料をもとに、戦後の漫画家や出版業界について描き切った一大評伝
「手塚治虫とトキワ荘」と聞くと、多くの人はこうしたイメージを抱くのではないでしょうか? 「手塚治虫が暮らしていたボロアパートに漫画家志望の若者たちが集まり、ときにマンガへの熱い想いを語り、ときに助け合いながらマンガを描き、やがて世間に認められ大成していった」――。 しかし、事実は必ずしもこの通りではないとのこと。たとえば、手塚治虫がトキワ荘に暮らしていた時期には、藤子不二雄Aも藤子・F・不二雄も、石ノ森章太郎も赤塚不二夫もまだ入居していませんでした。もうひとつ言えば、トキワ荘はけっしてボロアパートだったわけではなく、手塚治虫が入居したのは新築時だったといいます。 「『よく知られている物語』ほど、実像とは異なるイメージが流布するものだ」と述べるのは、『手塚治虫とトキワ荘』の著者・中川右介さん。本書は「伝説のベールを一枚ずつ剥ぎ取り、事実関係を整理する」という目的のもと、手塚治虫とトキワ荘グループと呼ばれる巨匠たちの業績を再構築し、日本マンガ出版史を解読した一冊となっています。 驚くべきは、本書のボリューム。二段組みの上に、あとがきまで含めるとおよそ400ページ近くにもなります。しかし、話を大げさに盛ったり、長々と余計なことを書いたりなどはいっさいナシ。膨大な数の資料をもとに、手塚治虫やその周りの漫画家たち、さらに彼らをとりまく編集者や出版社にいたるまで、事実に即したものごとやできごとを淡々と記しているのが特徴です。 でも、それならただの研究発表のようで、読んでいてもつまらないのではないか? そんなふうに思う人もいるかもしれません。けれど、非凡な才能を持った者たちの集まりだからか、これがどのエピソードも興味深くて引き込まれるものばかりなのです。 たとえば第二章「学年誌戦争」に登場する「手塚治虫の九州逃避行」のくだり。あまりの多忙さから手塚治虫が九州に逃亡したことがあるというのは有名な話ですが、当時手塚は11作もの連載を同時に抱えていたとか、手塚の身柄を確保するためさまざまな出版社の担当編集者たちが奔走したとか、松本零士のもとに突然、手塚から手伝いを乞う電報が届いたとか、こうした細かな情報を知るにつけ、読んでいるほうも手に汗握る気分に......。 現在、日本のポップカルチャーのアイコンともいえるマンガですが、戦後、日本の復興とともに、いかに漫画家と編集者が情熱を注いで盛り立ててきたのか、本書はそれがわかる一冊となっています。トキワ荘にこれだけ才能あふれる漫画家たちが集まったという奇跡の裏側を、ぜひ皆さんものぞいてみてください。
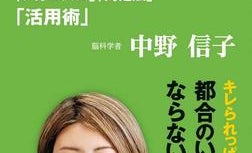
怒りの感情を脳科学的に分析 キレる人に振り回されない上手な対処法とは?
悪質なあおり運転、児童虐待、モンスターペアレントなど、ここ最近、怒りを抑えきれずに社会的な事件につながるケースが多発しています。こうした"キレる人"に遭遇したとき、私たちはどのように対処するのがよいのでしょうか。また、自分自身がキレやすい性格で、そうした自分とどう付き合えばよいか悩んでいる人も多いかもしれません。 いっぽうで、例えば人気芸人など、怒って見せながらも相手を不快にさせず、むしろ好感さえ抱かせるような上手なキレ方をする人たちもいます。そのポイントはどこにあるのでしょうか。 こうした"怒り"という感情について科学的に分析しながら、具体的な対処法、活用法を教えてくれるのが、今回ご紹介する『キレる!』です。著者は脳科学者、医学博士、認知科学者としてテレビコメンテーターとしても活躍する中野信子さん。本書は、対人関係において自分を守る「盾」となり「強み」にもなるような「キレるスキル」に光を当てた一冊になっています。 なぜ人は"キレる"のか、中野さんの専門分野である脳科学の立場から解説しているのが第二章。たとえば老人の攻撃性や頑固さは、理性を司る「前頭葉」が老化によって委縮することが原因であったり、子どもや夫(妻)など家族を束縛しコントロールしたがる人は、"愛情ホルモン"とも呼ばれる脳内物質オキシトシンが増えることで、"かわいさ余って憎さ百倍"とばかりに憎しみや妬みの感情も強まってしまうせいであったり。このように人が"キレる"仕組みは科学的に説明することができ、そのメカニズムを理解することで、「自分のキレる行為をコントロールできるようになったり、さらに、なぜ相手がキレるのか、タイミングや対処法が見えてきたりする」と中野さんは言います。 そして、第三章では"キレる"人に対する対処法を、第四章ではキレやすい自分との付き合い方をケース別に提案。たとえば「支配的で、立場を利用しパワハラをする会社の上司」への対処としては、とにかく「初動」が大事なのだそう。関係が深まってしまってから突然訴えても、相手はなかなか納得してくれないため、最初の理不尽に"怒り"を覚えたら、正しくキレて、はっきりと言い返すというのが効果的なのだとか。ほかにも、「普段はおとなしいのに、突然攻撃的になる人」「執拗なまでの『あおり運転』『ロードレイジ』」「疑い深く、キレやすい『暴走老人』」など私たちが日常生活でいつ遭遇してもおかしくない"キレる人"が挙げられており、ためになります。 「我慢は美徳」「努力したら報われる」といった考え方は日本には根強いですが、他人の努力などなんとも感じない毒々しい人がたくさんいるというのもまた事実。キレられっぱなしで都合のよい人にならないためにも、私たちが「キレるスキル」を身に着けることは必須といえるかもしれません。そして、上手に言い返すためには、豊富な語彙力もとても重要になってきます。さまざまなケースやパターンを学ぶための問答集としても、本書はきっと皆さんの役に立ってくれることと思います。

第161回芥川賞受賞作 なにげない日常に潜む、奇妙で滑稽な「狂気」
今回ご紹介するのは、今年7月に発表された第161回芥川賞を受賞した『むらさきのスカートの女』。『こちらあみ子』『あひる』『星の子』など、寡作ながらも作品を発表するごとに独自の視点と世界観で熱狂的な読者を増やし続けている今村夏子さんの最新作となります。 主人公の「わたし」は、近所に住む「むらさきのスカートの女」と呼ばれる女性のことが気になって仕方がありません。この女性はいつもむらさき色のスカートを履いて商店街に現れるため、このあたりではちょっとした有名人なのだといいます。彼女を長いこと観察しているうちに「友達になりたい」と強く思うようになった「わたし」は、自分と同じ職場で働くように密かに誘導します。それは見事に成功し、「わたし」はこれまで以上に「むらさきのスカートの女」の生活を観察し続けるように......。 あらすじだけ聞いても、「なぜ『わたし』はそこまで『むらさきのスカートの女』にこだわるの?」と疑問に感じた人も多いことでしょう。実は本書を読んでも、その理由は明確には明かされていません。そしておかしなことに、同じ職場で働くことになっても、「わたし」は「むらさきのスカートの女」と交流を持とうともしないのです。それなのに、彼女が朝出かける際に同じバスに乗り込んだり、休憩時間に所長と交わしている会話を盗み聞きしたり、使っているシャンプーまで把握していたりする「わたし」......。異常ともいえる執着心で「むらさきのスカートの女」の言動を延々と観察し続ける主人公の姿は、不気味でもありどこか滑稽でもあります。 「むらさきのスカートの女」は、仕事を始めてからどんどんと変化していきます。まず髪や体つきが健康的になり、爪にマニキュアを塗るようになり、香水をつけるようになり......。本書は一種の謎解き的な要素もあるため、ネタバレになることは詳しく書けないのですが、そうして次第に垢抜けていった彼女は、終盤である事件を起こしてしまいます。そこからが怒涛の展開。「わたし」がどのような行動をとるのかは、皆さんにもぜひ本書を読んで確かめていただきたいところです。
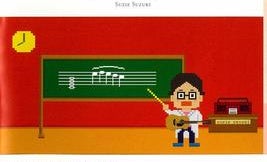
山下達郎、松田聖子、サザン...80年代ポップスの構造を理系的に分析!
ミュージシャンやアイドルが歌う曲が次から次へとヒットした、J-POP黄金時代ともいえる1980年代。そうした80年代の名曲の数々について、「白くて大きなベッドにあお向けに寝かせて、鋭いメスを持ってグリグリと、その構造を解体・解析していく」というイメージで書かれたのが、音楽評論家・スージー鈴木氏による『80年代音楽解体新書』です。 音楽評論というと、個人の感想や主観に重点を置いた「文系的」なものも多く見られますが、本書の大きな特徴となるのが、非常に「理系的」なアプローチをしているところ。では、「理系的な音楽評論」とはどのようなものかというと......? たとえば80年代の日本ポップスを代表する音楽家のひとり、山下達郎。彼の作品の強烈な個性として、「メジャーセブンス」というコード(和音)の徹底的な多用を著者は挙げます。その響きのイメージをあえて言葉にすると、「おしゃれ」「都会的」「哀愁」「センチメンタル」となるそうですが、これをイメージだけでなく、きちんと論理的に解き明かしていくのが著者の本領です。 コード界には、明るい響きのメジャー(長調)コードの代表として「ド・ミ・ソ」のCメジャー、そして暗い響きのマイナー(短調)コードの代表として「ミ・ソ・シ」のEマイナーというものがあります。先ほど出てきた「メジャーセブンス」には、このメジャーコードとマイナーコードの両方が入っていると著者は説明します。「ド・ミ・ソ」という普通のメジャーコードに、「シ」という奇妙でクセの強い音を混ぜたコード(「ド・ミ・ソ・シ」という音の組み合せ)になっている。もう少し詳しく言うと、「メジャーコードの上に、マイナーコードが乗っている」状態なのだとか。正確にカウントしたことはないものの、山下達郎の80年代の作品に限れば、9割以上の楽曲でこのメジャーセブンスが使われているのではないかと著者は書いています。 いっぽうで、メジャーセブンスの逆となるのが「マイナーセブンス」。これは「ラ・ド・ミ」というAマイナーのコードに、「ド・ミ・ソ」というCメジャーのコードが入っていて、「マイナーコードの上にメジャーコードが乗っている」構造の和音です。 これを図式で紹介したうえで、「メジャーセブンスは山下達郎、そしてマイナーセブンスははっぴいえんど」と自身の考えを加える著者。フォークロックバンド・はっぴいえんどの『12月の雨の日』という曲を例にとり、「1970年前後、新宿三丁目あたりの昼下がり、雨上がりの湿った空気の曇り空の下を、陰鬱な表情の長髪の若者が行きかっている」というイメージを広げます。そして、そうした「マイナーの上にメジャーが乗っている=70年代の新宿」から、「メジャーの上にマイナーが乗っている=80年代の青山」といった流れで、80年代の山下達郎によるメロウで都会的なシティ・ポップとを対比しています。 このように、図や表を多用し論理的に解説している本書。これまでなんとくイメージで受け止めていた曲も、その構造を明かされることで「だからこの曲は多くの人の心を惹きつけるのか」「このアーティストのすばらしさはここにあるのか」などストンと腑に落ちたりします。 ここ最近、ふたたび注目を集めている80年代J-POP。昔ファンだったという世代も、新たに聴き始めた若い世代も、本書を読めばきっとその魅力にさらに引き込まれるに違いありません。
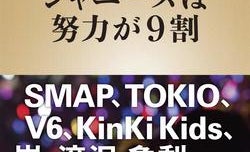
「YOU、やっちゃいなよ」に体現!? ジャニー喜多川流の人材育成力とは
7月9日に亡くなったジャニーズ事務所社長・ジャニー喜多川さんのお別れの会が4日営まれました。会場となった東京ドームには、近藤真彦さん、中居正広さん、木村拓哉さん、嵐、KinKi Kidsなど、多くの所属タレントが集結。その国民的かつ、ひとりとして個性が重ならない錚々たる顔ぶれに、あらためてジャニーさんの「才能を見出し、育てる」プロデューサーとしての手腕を感じた人も少なくなかったのではないでしょうか。 「最も多くのコンサートをプロデュースした人物」、「最も多くのナンバーワン・シングルをプロデュースした人物」、「チャート1位を獲得した歌手を最も多くプロデュースした人物」の3部門でギネスブックに掲載されたジャニーさん。彼を「日本で最も優秀な採用担当者」と評し、その偉大さで構築した"人を成長させる仕組み"について論じたのが本書『ジャニーズは努力が9割』です。著者は18歳でJr.オーディションを受けた生粋の「ジャニヲタ男子」にして、これまでに3冊の就活・キャリア関連の著書がある霜田明寛氏。 霜田氏はジャニーさんの才能発掘において、その人物が"今どうなのか"だけではなく"今後どうなるか"を見抜く、未来を見通す能力に長けていると指摘します。 「僕には20年後の顔が見えるんだよ」と自ら語っていたという、アイドルプロデューサーならではの「成長期の男子のルックス」はもちろん、競争の激しい芸能界で謙虚に努力し続けられる「人間性とやる気」も長期的目線で見極めるというのです。 むしろ、「踊りのうまい下手は関係ない。うまく踊れるなら、レッスンに出る必要がないでしょう。それよりも、人間性。やる気があって、人間的にすばらしければ、誰でもいいんです」というように、ジャニーさんは人物の物事に対する取り組み方を重視しました。本書は、このジャニーさん流の採用を「人事に関わる決定は、真摯さこそ唯一絶対の条件」と言った経営の神様・ドラッカーの説く組織論と重ね合わせます。このような方針のもと集められた"何者でもなかった"少年たちは、自らの頭で考えてそれぞれのやり方で努力し、やがて"特別な何かを成し遂げる"唯一無二のスターになっていくのです。 「ジャニーズの場合は、ジャニーさんが、きっかけを作ってくれて、あとは自分のことは自分で磨いていくというか。だから、ジャニイズムは人の数だけある。(中略)みんなちがっていいし、だからこそバラバラな個性がグループになったらおもしろくなったりもする」(本書p.215より) こちらは昨年芸能界を引退し、若手ジャニーズJr.の育成やプロデュースを担う株式会社ジャニーズアイランド社長に就任した滝沢秀明さんの言葉。滝沢さんの言うジャニイズムの精神は、今回のお別れの会でもナレーションで引用されたジャニーさんの口癖であり名言である「YOU、やっちゃいなよ」に体現されているかのようです。 人間というのは、こんな風に自分を全面的に受け入れ信頼してくれる一言を投げかけられたら、人生を変えるほどの努力を自ら始めるものなのかもしれません。ジャニーズ好きならずとも、誰かを育成する機会を持った人にもぜひ読んでほしい一冊です。

アメリカ人料理家の「魚」克服ドキュメント 日本で苦手に挑んだ彼女が得たものとは?
外国人観光客が築地や豊洲市場を訪れたり、お寿司屋さんで寿司をほおばったりといった光景は、いまや当たり前のものといってよいかもしれません。けれど、それは彼らにとってあくまでも異国での特別な体験でしかなく、ふだんは魚を切ることがこわく、魚を料理することに自信が持てないという人も多いようです。 そうした人たちを代表して(?)、「魚が苦手」というハードルに立ち向かったのが、本書『サカナ・レッスン 美味しい日本で寿司に死す』の著者でもあるキャサリーン・フリンさん。料理家である彼女自身も、当初は「多くのアメリカ人に比べると魚を食べることが好きなほうだ。魚を料理するほうだとも思う。しかし、魚を前にするとやはり戸惑う。正直少し、魚がこわい」というのが本当のところでした。けれど、「食文化から魚が切り離せない日本には、もしかすると『こわい魚』を克服するヒントがあるのではないか?」と考えるようになり、彼女は日本行きを決定。ここから彼女の大いなる挑戦がスタートすることに......! 「東京すしアカデミー新宿校」では魚のさばき方や寿司の握り方を教わったり、移転直前の築地市場ではマグロの競り場を見学したり、寿司屋では人生初の踊り食いを体験したり。また、日本人青年・クンペイの自宅では、日本の台所ならではの魚グリルに驚き、秋刀魚などを使った数々の家庭料理に舌鼓を打つ場面も。彼女の持ち前の好奇心とチャレンジ精神は、読んでいて心から拍手を送りたくなりますし、私たち日本人の心にも訴えかけるものがあります。 実は日本にも読者が多いキャサリーンさんですが、それは二作目の著書『ダメ女たちの人生を変えた奇跡の料理教室』によるところが大きい様子。料理が苦手で自分を「ダメ女」と思ってしまっている女性たちに料理の基本的な技術を教え、人生にも家事にも勇敢な「家庭料理人」に変えていくというノンフィクションは、日本でも異例のヒットに。日本テレビ系列のテレビ番組『世界一受けたい授業』から依頼を受け、出演を果たすほどの反響を呼びました。 そんなキャサリーンさんや彼女の著書から私たちが学べることは、「苦手」に対する気持ちの持ち方や付き合い方、乗り越える方法ではないでしょうか。日本人であっても魚をさばくのがこわいという人は多いし、魚に限らなくても、苦手なものは誰にだってある。無理して対峙する必要はないかもしれませんが、逃げないで一歩踏み出してみると、人生はきっと豊かなものになる。彼女の一連の「サカナ・レッスン」を通して、そうした感銘を受ける人は多いことと思います。 では、キャサリーンさん自身が今回のチャレンジで得たものは何か。エピローグで彼女は「いまとなっては、五千マイルも離れた国に、たくさんの友達がいる。多くの家庭料理人とわたしはつながることができている。わたしの食品棚には七種類の醤油があって、日本製の魚グリルが二台も狭いキッチンに鎮座している」と書いています。魚のさばき方や調理法だけでなく、ほかにもいろいろなものを手に入れた彼女ですが、それに飽きることなく「わたしの挑戦ははじまったばかりだ」と続けていることには感心するばかり。いくつになってもチャレンジすることはけっして遅くない、そしてそこにはたくさんの楽しみや可能性が待っていることを本書は教えてくれます。

無意識のうちに縛られている言葉の数々... その呪縛を解く方法とは?
「呪いの言葉」と聞くと、おとぎ話の中だけに出てくるもののように思えますが、どうやら実際には私たちが暮らすこの世界にもあふれかえっているようです。 たとえば、長時間労働や不払い残業、パワハラ、セクハラといった問題に声をあげる者に対して投げかけられる、「嫌なら辞めればいい」という言葉。これは、「その仕事を選んだのはおまえだろう。辞めずにいるのも、おまえがそれを選んでいるからだろう。だったら文句を言うなよ」と労働者の側に問題があるかのように仕立て上げる、典型的な「呪いの言葉」といえるかもしれません。 そう、現代における「呪いの言葉」とは、相手の思考の枠組みを縛り、相手を心理的な葛藤の中に押し込め、問題のある状況に閉じ込めておくために、悪意を持って発せられる言葉なのです。 では、「呪いの言葉」にからめとられないようにするには、私たちはどうすればよいのでしょうか? そのケーススタディとして役立つのが、本書『呪いの言葉の解きかた』。著者の上西充子さんが、労働、ジェンダー、政治といった私たちの周りに蔓延する「呪いの言葉」とその解きかたをわかりやすく教えてくれます。 上西さんは本書で、「大事なのは、『相手の土俵に乗せられない』ことだ。『相手の土俵に乗せられている』と気づいたら、そこから降りることだ」と書いています。呪いの言葉がかけられたときには、「なぜ、あなたは『呪いの言葉』を私に投げるのか」「あなたは私を逃げ出せないように、縛り付けておきたいのですね」と問うことが有効だそう。先ほどの「嫌なら辞めればいい」というひと言に対してなら、「『どうせ辞められないんだろう? だったら理不尽にも耐えろ』というわけですね」と切り返す。実際に口に出すのが難しいなら心の中ででもよいので、問い返すことによって、呪いの言葉を投げつけられた者は、その言葉の呪縛から一時期的にせよ、精神的に距離を置くことができます。呪いの言葉の呪縛の外に出られれば、柔軟に考え、行動することが可能になります。問題をとらえ直したり、どう対抗できるかに発想を変えたり、具体的な状況改善の糸口が見えてきたりといったこともあるかもしれません。 ほかにも、「文句を言うな」「逆らっても無駄」「君だって一員なんだから」「母親なんだからしっかり」「なぜもっとがんばれないのか」などなど......本書を読めば、私たちの身の回りにはどれほど多くの「呪いの言葉」があり、無意識のうちにどれほどそうした言葉にとらわれているかに気づくはず。まずはこの「気づきを得る」ことだけでも、ずいぶん世の中の見方が変わってくるのではないでしょうか。また、誰かが自分に届けてくれた「灯火の言葉」や、私たち自身の中から湧き出てきた「湧き水の言葉」といった「呪いの言葉」とは対照的な言葉も紹介されており、希望の光を感じることもできます。 労働、ジェンダー、政治と聞くと難しい内容に感じる人もいるかもしれませんが、文章が非常にわかりやすく読みやすいのも本書の魅力。ドラマ化もされたコミック『逃げるは恥だが役に立つ』やテレビドラマ『カルテット』、コミック『陰陽師』なども引き合いに出しており、若い人にも読みやすいのではないかと思います。「しかたがない」「自分が我慢すればいい」とあきらめることはやめ、意識的に「呪いの言葉」の呪縛の外に出る術を皆さんも本書から学んでみてはいかがでしょうか。
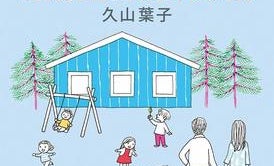
日本のママは手作りし過ぎ!? 幼保無償化の前に知っておきたい、スウェーデン式"手抜き"子育て
かつて一大旋風を巻き起こした「保育園落ちた日本死ね」(2016年)から3年、国としても「待機児童ゼロ」へ取り組まざるを得なくなってきています。 とはいえ保育園に入れたとしても、そこで保護者を待ち受けるのが様々な試練。たとえば、入園準備では大量の食事エプロンや手拭きタオルへの名前付けに始まり、マジックでオムツに1枚1枚名前を書くこと、さらに使ったオムツを持って帰る「オムツ持ち帰り問題」、毎日出る大量の洗濯物...など。そして共働きでの家事負担も、ママの肩に重くのしかかりがちです。 今回ご紹介する書籍『スウェーデンの保育園には待機児童はいない――移住して分かった子育てに優しい社会の暮らし』の著者、久山葉子さんも、そんな疲弊したママの1人でした。 理想の子育て環境を求めて2010年、「待機児童がいない国」スウェーデンに移住後は、サダム・フセインの愛人の自伝『生き抜いた私 サダム・フセインに蹂躙され続けた30年間の告白』(主婦の友社刊)の翻訳を皮切りに、『悪意』(東京創元社刊)など手掛けた翻訳は多数。いまやスウェーデン・ミステリ翻訳家として活躍中の久山さんですが、初のエッセイとなる本書では、日本での保育園生活を以下のように振り返っています。 「しかし何よりも、"子供の持ち物を手作りするいいお母さん"を強要されるのが息苦しかった」(本書より) 「よい親とは、特に、よいお母さんとはこうあるべき――子供が保育園という社会にデビューするなり、世間からのプレッシャーにさらされることに気づいた」(本書より) スウェーデンの保育園は、オムツはパック丸ごと1袋持っていけばよく、タオルはすべて使い捨てのペーパータオル、お昼寝布団のシーツは園で洗濯。さらに昼食だけでなく朝食も提供されるのが普通であり、保護者の労力も精神的負担も非常に少ないことに驚きます。 また、各家庭の家事育児についても「スウェーデンに来て、こんなに手を抜いてもいいものなのかと驚かされた」(本書より)と述べ、非常に"手抜き"している点に言及。たとえば、野菜を切るだけの「野菜スティック」、焼くだけの冷凍食品の多用など、パパママが夕食づくりにかける時間は平均20分。 「日本のパパママは、もっと食事作りに手を抜いていいと思うし、それでも世界規模で見れば毎日すごいご馳走を作っているのだと自分をほめてあげてほしい」(本書より) 夫婦でそれぞれ働いているのだから、そもそも料理に手間をかけることは難しいこと。合理的に考えて家事ハードルを下げなければ、共働き生活は成立しないと指摘する本書からは、スウェーデンでは、日本のようにママ個人の努力を"美徳"とみなす意識はなく、子供は国全体で育てるものであるというマインドが伝わってきます。日本ではいよいよ今年10月から幼児教育や保育園の無償化が始まりますが、保育園問題を考えるときに読んでおきたい、必読の1冊と言えるでしょう。

ドラマ化も決定! 歌姫・浜崎あゆみへの取材を基にした自伝的小説
8月1日に発売されるやいなや、メディアでも大々的に取り上げられ、話題を呼んだ『M 愛すべき人がいて』。ノンフィクション作家の小松成美さんが歌手・浜崎あゆみさんへの取材をもとに、歌姫としてスターダムに駆け上る過程や運命的な男性との恋愛秘話を描いた一冊となっており、初週で3.8万部を売り上げるヒットを記録しています。 「事実に基づくフィクション」としながらも、最後のページでは浜崎あゆみさんによる「自分の身を滅ぼすほど、ひとりの男性を愛しました」との文章を掲載している本書。この"ひとりの男性"が現・エイベックス会長の松浦勝人氏であることは本書でも実名で明かされており、"一時代を築いた音楽プロデューサーと歌姫の恋愛"といった暴露本的な意味合いで、興味をそそられ購入した人も多そうです。 さて、内容についてですが、本書は「私は」という"あゆ(浜崎あゆみさん)"目線で情感たっぷりに書かれており、小説のような体裁で進んでいきます。展開もたいへんドラマチック。17歳のときに六本木のクラブ「ヴェルファーレ」のVIPルームで初めて松浦氏と出会い、「大丈夫、俺を信じろ」という松浦氏の言葉にしたがって歌手デビュー。ある日突然、「あゆ、ニューヨークへ行ってこい」と松浦氏に告げられ、単身でボイストレーニングに赴くことに。デビュー後、ハイスピードで変わっていく環境の中、松浦氏への恋心を打ち明ける"あゆ"。松浦氏はその思いに応え、"あゆ"の母親に「あゆみさんと付き合っています。真剣です」と交際宣言し、そのままふたりフェラーリに乗ってドライブに繰り出す......もう読んでいて、すべてがドラマの1シーンのように脳内に浮かび上がります! ここでひとつ重要なポイントとしてあるのは、こうした松浦氏への思いがすべて彼女の楽曲の歌詞になっていたという点。松浦氏とのエピソードの合間合間に"あゆ"の歌詞が挟まれ、「この曲を作詞したときは、松浦氏とこういう状況だったのか」「こんな思いを抱えていたときに生まれた歌だったのか」と読者は知らされることとなります。 なお、本書は2020年春に連続ドラマ化との報道も。誰が"あゆ"を演じるのか、どんな演出がされるのかなど、今後もまだまだ注目が集まることとなりそうです。

100年経たずに人口半減!? 20年後の日本人はどこに暮らしているのか
現在、日本で急速に進んでいる少子高齢化。厚生労働省の人口動態統計(年間推計)によると、2018年の減少幅は44万8000人となり、ついに40万人台に突入したそうです。今後も減少幅は年を追うごとに拡大し、わずか40年後には現在より3割ほど少ない「7割国家」となり、100年も経たないうちに人口は半減すると予測されるといいます。 このようなスピードとボリュームで人口が減っていき、少子高齢化が進んだ結果、私たちの経済活動や国民生活はどうなってしまうのでしょうか? この問題に2つのアプローチで挑んでいるのが本書『未来の地図帳』です。第1部では主な大都市を中心に人々が移動する現状を見ていき、第2部では、2015年を起点として2045年までの日本列島がどのように塗り替えられていくかを分析しています。 第1部は「現在の人口減少地図」ですが、例として首都である東京についての箇所を見てみましょう。現時点で、データで見ると東京の一極集中は依然というより、むしろ拡大し続けているといいます。東京圏の学校に進学し、出身地に戻らない若者が少なくないだけでなく、地方から東京圏に仕事を求めて出てくる女性の増大が一極集中の流れを押し上げているそう。東京一極集中は是正されたほうがよいものの、著者の河合雅司氏は「もはや一極集中を前提として人口減少時代を考えなければなるまい」として、「人口減少日本の中において、東京圏を全く違う歩みを辿る「外国」と位置づけ、非東京圏の各エリアは人口が減っても成り立つ仕組みへ変換することで、共存する道を探っていくほうが現実的」だと述べています。 ほかにも、「『西の都』の人口拡大を下支えしているのは、外国人住民」(大阪市)、「名古屋市最大の懸念材料は、リニア新幹線と広すぎる道路」(名古屋圏)、「周辺から人を集めきれず、"磁力"の弱い広島市」(中国)など、現在を生きている人々が日本の国土をどのように動いているのかを知れる興味深い見出しが並んでいます。 第2部「未来の日本ランキング」では、20年後の私たちがどこに暮らしているかが詳しく解説されています。東京は日本の中でも「外国」と位置づけるべきと先述がありましたが、今後、「東京圏という外国」は高齢化で苦しむこととなる模様。2025年には練馬・足立・葛飾・杉並・北区で4人に1人が高齢者となるなど、「ビジネス優先」「若者中心」できた23区内の多くの地区で「街の存り様」が大きく変わってくるようです。 また、地方に目をやると、政令指定都市は極端に明暗が分かれる、県庁所在地・地方都市は不便さの増すエリアが拡大する、などが予想されるそう。また、2045年には出産期の女性が一人になる村が出てくるほか、全国17の町村でも1ケタになるとの予定だったり、小樽、横手、河内長野では赤ちゃんが6割減になったりなど、少子化もますます深刻さを増していることが考えられます。 なんだかネガティブな見通しばかりで明るい未来が思い描けなくなってしまいそうですが、第3部では日本(人)がなすべきことが示されているのが救いです。このままでは少子高齢化と人口減少は進んでいくばかりですが、今からでも取り組み方次第で「未来」は書き換えが可能だと河合氏は本書で述べています。 今の日本の現状がどのようになっていて、今後どうなっていくのか。私たちが生き残るために取るべき対策は何なのか。その手引書となる本書を読んで、皆さんもぜひ考えてみてください。

ある日、恋人がストーカーに…“被害者”である著者が綴る衝撃の実話
後を絶たないストーカー被害。2018年の相談件数は2万1556件、前年より1523件減少したとはいえ、2万件を超えたのは6年連続でした。数字だけではあまり実感がわかない人も多いかもしれませんが、自分の身に降りかかることもあり得るのです。 本作『ストーカーとの七〇〇日戦争』は、著者の内澤旬子さん自身がストーカー被害に遭い、恐怖しながら理不尽さと戦ったノンフィクション。そのリアルさに読者は、ストーカー被害という身近でありながら遠い世界を追体験することになるでしょう。 内澤さんといえば、イラストルポライターとして『世界屠畜紀行』など世界の辺境を旅して日本人の知らない世界を伝えるイメージが強い作家。本作でも、ストーカーという想像を絶する世界を私たちに教えてくれます。 ストーカーに遭う発端となったのは、些細なことでした。きっかけは、8ヶ月交際した元恋人Aからの「家に遊びに行きたい」という申し出を断ったこと。16年4月初旬、Aは突如として内澤さんのストーカーに豹変したのです。 内澤さんは14年に東京から小豆島に移住し、海が見える家でヤギのカヨと一緒に平穏な生活を送っていました。マッチングサイトで、セックスでも不倫でも結婚目的でもない、誠意ある交際相手を求めていました。知り合ったAはその理想とはかけ離れたものでした。 「お前はなんでも自分が正しいと思っている」が口癖で、内澤さんの言うことを聞き入れようとしないA。嫌気が差して別れようとしていた矢先、それを察したかたのように、生活に支障が出るほど、電話が鳴りやまない日々が。ついに別れ話を切り出すも、納得のいかないAは、「全部自分が悪かった。お前の言う通りに直すからやり直そう」と交際継続の姿勢を崩しませんでした。しばらく、一進一退の攻防が続くことになります。 しびれを切らした内澤さんは、ついに「ストーカーに近い行為」「生活相談課に相談」などという言葉を投入します。しかし、このことがAを逆上させることになります。 Aは「俺をストーカー呼ばわりしたことは許せない」として、知り合いのライターにこれまでの交際を曝露してやると宣言。鬱病になったのも、内澤さんから暗い愚痴ばかり聞かされたからであり、「損害賠償で訴えてやる」とも脅されます。被害はさらに悪化の一途をたどっていきます。 メッセージは5分おきに届くようになり、「島に行ってめちゃくちゃにしてやる」と怒りを募らせるばかり。「怖がっていないように」と冷静に対処を重ねていくも、それが後に仇となることに。そしてついに、Aが島にやってきてしまい......。 実際の被害者の視点から恐怖や不安、緊迫する雰囲気など臨場感あふれる描写に圧巻。ドキュメンタリーとしての読みごたえはさることながら、法整備の不十分さ、刑期の軽さなど様々な問題点を浮かび上がらせます。 著者の事例からもわかるように、相手がふとしたことからストーカー化して、いつ被害に遭うかわかりません。本書はストーカー被害にあったらどこに相談にすればいいのか、警察はどこまで動いてくれるのかなども知ることできる解説書としても秀逸。すべての人に手に取ってほしい一冊といえそうです。
特集special feature

ザビエルはインスタグラマー、明智光秀は知恵袋に相談!? クスリとしながら学べる歴史本
とつぜん突拍子もない話をしますが、もしも戦国時代にスマホがあったなら、あの武将やあの歴史的事件はいったいどんなふうになっていたでしょうか? 織田信長はLINEのグループトークを使って「桶狭間の戦い」を逆転勝利へ!? 武田信玄は上杉謙信から送られた塩のAmazonレビューを書く!? 「本能寺の変」を前に明智光秀はYahoo!知恵袋で相談する!? ......なーんてことも、もしかしたらあったりして。 そんなユニークな視点から激動の戦国時代を一冊にまとめたのが本書『インスタ映えする戦国時代』です。著者は、日本史に登場する偉人やできごとを「現代の身近なもの」に置き換える歴史パロディ画像が人気を呼び、ツイッターでのフォロワー数が10万人を超えるというスエヒロさん。思わずクスリと笑ってしまう彼のパロディ画像は、皆さんもツイッターで一度は目にしたことがあるかもしれません。 ここで本書の中身をいくつかご紹介しましょう。たとえば、宣教師フランシスコ・ザビエルのインスタ。もうこのワードを耳にしただけでも「どんな写真アップしてるの?」「ハッシュタグは!?」と興味津々になってしまいますが、投稿している写真は歴史の教科書にもよく出てくる自画像。それとともに「先日から日本に布教にきてます! 薩摩のほうにいるのですがめっちゃ暑い! 早く京に行きたい~」との自身の書き込みが。そして「#布教中」「#イエズス会」「#キリスト教広めたい!」といったハッシュタグがつけられています。はるか昔の歴史上の人物でしかなかったザビエルに、なんだかめちゃくちゃ親近感がわいてきた......! もうひとつ。明智光秀が参加者同士で作るQ&Aサイト「Yahoo!知恵袋」に投稿したのは「【相談】上司の武将が横暴で悩んでいます...これはパワハラでしょうか?」という質問。本能寺の変の原因として「主君である織田信長に虐げられていたから」という説もありますが、現代に置き換えてみるとたしかに今で言うところの"パワハラ"にあたるかもしれません。そう考えると、これまた身近な問題に感じられてきますね。そして本書は細部まで凝っているところも特長。このネタであれば、「ベストアンサーに選ばれた回答」として「owari_monkey」さんの回答を掲載しているのですが、「たとえば、雪の日に上司のぞうりを懐で温めてみたりするとか、まずは『小さな信頼』を得るところから始めてみてはいかがでしょうか」とアドバイスしています。この名前、回答内容......これはまさしくあの歴史上の人物。歴史好きな人であればニヤリとしちゃいそうです。 本書について「戦国時代の出来事を身のまわりに置き換えて想像してみると、当時の人々や出来事、空気をよりリアルに感じることができるような気がしますし、それによって遠い時代の出来事をより鮮明に再体験できるような気がします」とスエヒロさん。これまでにない、今の時代ならではのニュータイプの歴史本と言えるのではないでしょうか。おふざけが多分に含まれているとはいえ、並びが史実順になっていて大きな流れをつかむことができたり、解説やコラムも併記されていたりするので、歴史を楽しみながら勉強したい学生の皆さんにもおすすめです。
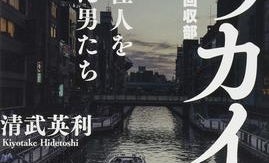
「一生、取り立てる」 不良債権の取り立てに奮闘するトッカイ(特別回収部)の攻防
今の若い世代は知らない人も多いであろう「住宅金融専門会社」、略して「住専」。1970年代に銀行などが設立した、個人向け住宅ローンをあつかったノンバンクのことです。当時、銀行は企業向け融資を優先しており、個人向けには熱心ではなかったため、大蔵省主導のもと銀行などの金融機関が共同出資してこうした専門会社が設立されることになったという背景があります。 しかしその後、バブル経済の崩壊により住専は巨額の不良債権を抱えることに。住専8社のうち7社が経営破綻し、6850億円もの公的資金が投入されることとなったのですが、これは世論の強烈な反発を招き、その是非をめぐっては国会を巻き込んでの政治問題へと発展しました。 本書は、この不良債権取り立てに奮闘する国策会社(=整理回収機構)で働く男たちの熱い戦いを描いた一冊です。「トッカイ(特別回収部)」と呼ばれた彼らは経営破綻した住専や銀行からさまざまな理由で選ばれ、借り手の側から今度は取り立てる側へと回り、大口で悪質な反社会的債権者を担当したといいます。バブル経済に踊った怪商に借金王、ヤクザ......こうした一筋縄では行かない相手との攻防や彼らをジワジワと追い詰めていく様子が、手に汗握る一大ドキュメントとして描かれています。 そう、本書はけっしてフィクションではなく、著者の清武英利氏が3年半もの間、関係者のところへ通って丹念に取材し書き上げたノンフィクション。清武氏は整理回収機構の元役員から「彼らの不良債権回収は将棋に似ている」という話を聞き、トッカイの人々を描きたいと強く願ったのだといいます。トッカイにいた多くは、勤めていた住専や金融機関がつぶれ、そこから大蔵官僚と政治家がしつらえた取り立ての盤上に将棋の駒のように打ち込まれた者たち。離脱が許されるわけではない、しかし展望を考えることもできない大混乱の現場の中で、「彼らが不安を抱えながらどう生きたか、どこへ去っていったのか、追ってみたいと私は思った」と清武氏はあとがきで書いています。 整理回収機構の前身となる住宅金融債権管理機構が設立されたのは1996年で、初代社長に就任したのは「平成の鬼平」と呼ばれた中坊公平元日弁連会長でしたが、「一生、取り立てる」という彼の遺訓は今もまだ生き続けているといいます。当時2000人超がいた組織は現在300数十人へと減ってはいるものの、今も回収機構は存在し、悪質債務者から取り立てをおこなっているそう。平成から令和へと移り、住管機構から数えると間もなく20年という節目を迎えようとする今でも、本書に登場する不動産会社元社長・西山正彦氏への回収は現在進行形で進められているというから驚かされます。 著者の清武氏は元読売新聞社の社会部記者であり、読売巨人軍の球団代表や編成本部長を務めたこともある人物。『石つぶて 警視庁 二課刑事の残したもの』や『しんがり 山一證券 最後の12人』などの著書でも知られる名うての作家の作品には、皆さんのページをめくる手もきっと止まらなくなることでしょう。
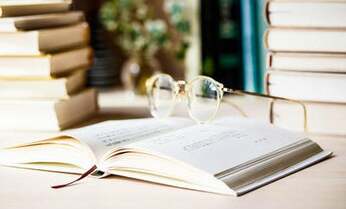

「幸せでも不倫する人」の意外な動機とは? 人気心理療法士が分析
直近では原田龍二に後藤真希......。多発するスキャンダルによって、不倫の注目度がますます高まる中で、世間の目もこれまでよりも厳しくなっています。こうした不倫問題は、日本だけでなく万国共通の問題のようです。 本書『不倫と結婚』(晶文社)によれば、米国を例にとると、不倫には普遍的な定義がないなどの理由からデータ上では女性の26~70%、男性は33~75%と相当な幅があるとしながらも、不倫が増加しているのは紛れもない事実だとしています。 世界中で多くのカップルを見てきた心理療法士で著者のエスター・ペレル氏は、本書の中で「1990年以降、男性の不倫率は変わっていないのに、女性のそれは40%も増加している」と女性の不倫増加が背景にあると言及。「もはや浮気をするのに自宅を出る必要がない」と、普及したネットやアプリによる影響が大きいとも述べています。 そのように本書では、ペレル氏が数多くの不倫夫婦へのカウンセリングしてきた経験を踏まえながら、不倫をさまざまな角度から論じています。例えば、不倫には三つの構成要素があると分析。「秘密」「性の魔力」「精神的な関わり」のうち一つ、もしくはいくつかが含まれているといいます。 まず「秘密」は「不倫を不倫たらしめる筆頭の原則」と評します。秘密であることが性欲を掻き立てるものであるとしたうえで、"罪悪感と喜びのミックス"なんだとか。2番目の「性の魔力」は、セックス行為そのものよりも、「欲情されたい」「自分を特別な存在だと感じたい」などの欲望が充足されるという"魔力"が関係していると分析します。 最後は「精神的な関わり」。言うなれば、それは"情熱的な愛の開花"。「愛がどんなものか知っているつもりでした。でも、こんな気持ちは生まれて初めてなんです」というよくあるセリフがまさにそれだというのです。一方で、あの女性とは「肉体関係だけだ」と精神面での関わりを最小限に見せようとする言い訳も該当するとのこと。 ペレル氏は「人はなぜ不倫するのか?」という不倫問題の根幹にも触れています。中でも興味深いのは「幸せな人でも不倫する」ということ。これまで、不倫の動機はセックスレスや孤独感などの問題から、不倫で"結婚の機能不全"を補うという面で語られがちでした。 しかし、何年も何十年も貞節を守り、思いやりのある円熟した"完璧な夫婦"に見えたとしても、不倫に走ってしまうというケースが少なくありませんでした。ペレル氏は、カウンセリングを進めていくうちに、その動機が「新たな自分探し」だとわかったのです。 「繰り返し耳にするテーマが一つあった。それは新しい(または失われた)アイデンティティの探求、つまり自己発見という形の不倫だ。こういった探求者には、不倫が何らかの問題の症状というよりは、成長や変化を伴った発展的な体験だと描写されることが多い。(中略)求めているのは、新しい恋人よりむしろ新バージョンの自分だ」(本書より) 本書では、「私の人生は恵まれた人生」と自分で言えるほど完璧な女性が登場。50歳のいま、「私がデートするような相手じゃない」と揶揄する男性との不倫が辞められない......。彼女に一体何があったのか、結婚生活の問題ではなく彼女の人生の問題に迫っています。 豊富な事例を交えながら不倫に陥る動機やその代償など、不倫のすべてを知れる本書。反面教師として活用すれば、より良い結婚生活を送るためのバイブルとなりそうです。

1本5000円なのにバカ売れ!?「レンコン」農家のサクセスストーリー
1本5000円という超高級品ながら、生産が追い付かないほどの大人気。銀座、神楽坂、赤坂から、ニューヨーク、パリ、ドイツにいたるまで、国内外の超高級料理店の数々でも食材として使われ、2018年にはなんと約1億円もの売り上げを計上。そんな驚くべき、茨城県産の"レンコン"があるのをご存知でしょうか? この"1本5000円のレンコン"を構想し、見事ビジネスとして成功を収めたのが、民俗学の研究者であると同時に、レンコン生産農業に従事する野口憲一さん。野口さんによる本書『1本5000円のレンコンがバカ売れする理由』では、レンコン農家に生まれた野口さんが、大学・大学院で学んだ民俗学や社会学の考え方を駆使しながら、現在の"バカ売れ"状態を成し遂げるにいたるまでの、レンコンを巡る紆余曲折の道のりが記されています。 1本5000円という高価格でありながら、なぜこれほどまでに大人気となったのか――。本書では、レンコン農家の抱える問題を前に、物の売れる理由を考え、それを愚直に追求していった野口さんの地道な努力が綴られています。 いまではどこのスーパーでも一年中見かけるレンコンですが、かつてレンコンは高級野菜の代名詞でした。しかし1970年にはじまった減反政策によって米の作付けが制限されると、それまで米を生産していた多くの稲作農家が、わずか20年間に一挙にレンコン生産農業へと舵を切ったため、レンコン生産面積が飛躍的に拡大。次第にレンコンは高級野菜から大衆化の道を辿っていったのだといいます。 しかし大衆化は、レンコン農家に苦難をもたらしました。供給量が需要を圧倒的に超えることにより商品価値は低下し、価格が暴落。収入を維持するため、耐病性に優れ、収穫量の多い品種を開発したことも、ますます大衆化に拍車をかけ、もはや他の生産地に台風が来て収穫ができなくなることを願うしかないという、仕事に対する矜持をも失ってしまう悪循環に陥ってしまったのです。 「農家が仕事に対するやり甲斐と矜持を取り戻し、利益も確保できるようにするにはどうしたらいいのか。民俗学者として、レンコン生産農家として、僕はそのような問題意識に苛まれていました」(本書より) こうした状況を前に野口さんは、レンコンに"原価と製造コスト以外の何らかの価値"を付与し、レンコンをブランド化するべく格闘を開始。民俗学の知識を生かしながら、"伝統の創造"にひとつの可能性を見出します。恵方巻きや七草粥といった"伝統"が、ときに商業的な理由によって新たに創られてきたように、意図的に伝統を創ろうと考えたのです。 そこで曾祖父の代である大正年間には既にレンコンを生産していたことに着目し、"大正15年創業"という老舗感を押し出すことに。そのひとつとして、5000円という値段に見合い、なおかつ"大正15年創業"のイメージを具現化した"和モダン"をテーマとする、高級感溢れる豪華なオリジナル箱を作製します。 しかし、そんな自信作も、はじめはまったく売れなかったといいます。それでも野口さんは諦めませんでした。ここから本書では、コストばかりが嵩んで家族にも反対される苦境のなかでも、独自の営業を続け、人脈を徐々に築き、1本5000円のレンコンが次第に世に出回っていく様子が描かれていきますが、そのマーケティングやブランディングはもちろん、特筆すべきは、野口さんがバカ売れの最たる要因を"両親や先祖から引き継いだ信念や感性、そして身体性"に見出していること。それにより本書は、単なるマーケティングやブランディング論に留まらない、レンコン農家としての矜持も強く心に響いてくる一冊となっています。

数多くの凶悪事件を取材してきた著者がつづる、連続殺人犯10人の肉声
ふだん仕事をしたり日常生活を送ったりしている中で、皆さんも一度や二度は自分の常識や道徳がまったく通じない相手と出会ったことがあるかと思います。同じ人間なのに、まるで宇宙人と話しているかのような心の通じなさには驚き、恐れや怒りを感じ、ときには虚無感すら感じることも......。 今回ご紹介する『連続殺人犯』は、数多くの殺人事件を取材してきた著者・小野一光さんが、拘置所の面会室で、現場で、震撼させられた連続殺人犯10人の声を綴ったという一冊。本書を読むと、ここに登場する人物たちに対しても同じような感覚を味わうことになるかもしれません。 なぜなら、誰しも一瞬の激情にかられて人を殺してしまう可能性はあるけれど、何度も、何人も殺害するという行為は生命を軽視していないとできないことであり、普通の人にとっては理解の範疇を超えるものだからです。小野さんは本書で、連続殺人は「ある種の条件が揃った人だけ」ができることだといい、彼らのことを「悪に選り分けられた者たち」という言葉で表しています。 本書で取り上げているのは、北村孝紘、松永太、畠山鈴香、角田美代子、筧千佐子といった連続殺人犯たち。今も人々の記憶に残る世間を震撼させた人物ばかりですが、全員ではないにしろ著者が実際に彼らに会い、会話をしているというのが、本書が他のルポと比べて稀有な点です。 たとえば、文庫版になるにあたってあらたに加筆されたのが近畿連続青酸死事件の筧千佐子の章ですが、彼女は見た目はごく普通のおばちゃん。小野さんは彼女の中にどんな殺意が眠っているのかが気にかかり面会を重ねますが、彼女との対話の多くが"暖簾に腕押し"で終わります。都合のよい質問には機嫌よく答え、ときには真実や本心の混じった言葉も漏らす。けれど、自分の不利な材料であると気づけば、記憶の減退を口にしたり平気で嘘をついたりして逃れる。その繰り返しの末に、22回目の面会で小野さんは拒絶される結果に。これは読んでいるほうにとっても何とも言えないもどかしさや不快感を感じさせられます。 ほかにも、人間の感情がないかのような者や、明るく晴れやかな表情で自身の無実を訴える者、捕まった後に自身の命を絶ってしまった者なども出てきます。もし、彼らがよんどころない事情や被害者に対する罪の意識などを少しでも語っているのなら、読者としては少しのカタルシスや安堵感を得ることができたかもしれません。しかし、どう考えても理解や共感を示せないケースが多すぎて途方に暮れてしまいます。 では同じような無力感を感じつつも、著者はなぜ連続殺人犯への取材をやめないのか。それは「次はどんな理解不能なことに出会うのだろうかという、人間の多様性への興味」があるからだといいます。皆さんの中にも同様に、自分の常識を超えた人間におののきつつもその一断面を見たい、知りたいという人がいるなら、きっと本書を興味深く感じられるのではないでしょうか。 最後に、陰惨な事件やモンスターのような殺人犯が登場する本書ですが、読後はけっして暗たんとするばかりではありません。それは、著者が遺族など被害者側にも可能なかぎり取材をしており、彼らへの配慮あるまなざしが感じられる点。そして一部ではありますが、出てくる人物の中にも犯行後に悔恨の情を持ちながら粛々と日々を過ごしている者がいること。これは本書における一縷の希望といってもよいかもしれません。
カテゴリから探す
エンタメ

NEW

























