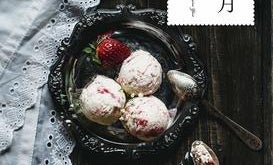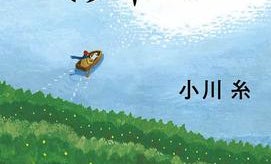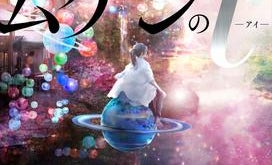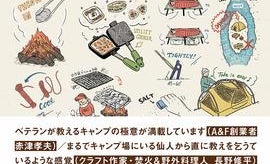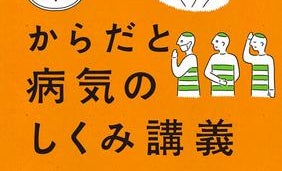
「なぜ風邪を引くの?」「血液型占いは信じられる?」 阪大教授による病理学の超・入門書
昔に比べ、治らなかった病気が治せるようになったり、選べる治療法が増えたりと、大きく進歩している医療の分野。その分、患者自身に大事な選択や決断がゆだねられるようになった部分が多いそうです。間違った判断をしないために、私たちはある程度、自分たちでも体の仕組みについて知っておく必要があるのかもしれません。 その助けとなってくれるのが仲野 徹さんの著書『からだと病気のしくみ講義』。本書では、血液系、循環器系、呼吸器系、消化器系という4つのシステムを取り上げ、そのつながりや体と病気の仕組みなどについて解説しています。 病理学の本と聞くと分厚くて難解なイメージを抱く人も多いかと思いますが、本書はそんなことはありません。医学的な専門用語などは使われておらず、活字も大きく読みやすい。さらに、大阪大学大学院で病理学の教授を務める仲野さんの大阪弁がいたるところに出ていて、非常にとっつきやすいです。気のいいおじさんの話を面白おかしく聞いているような、そんな気分で読み進められます。 たとえば第1章「血液の中身のはなし」では、赤血球や血小板などの基本的な説明がされているのはもちろんのこと、「『免疫力を上げる』ってどういうこと?」や「血液型占いは信じられる?」といった項目も。身近な話題が取り入れられていて興味をそそられますね。 ちなみに血液型占いは「まったく根拠がないことがわかっています」と仲野さん。「なのによく『お前は変わってるからB型やろ』と言われて閉口しています。ホンマにB型やから余計に腹が立ちます」(本書より)なんて書かれていて、思わず笑ってしまいます。これには全力でうなずきたくなるB型の人が多いのでは......? わずか100ページほどの本書について、仲野さんは「短い本なので、本当に基礎的なこと、入り口みたいなことしか書けません」(本書より)と「おわりに」で記しています。しかし、一般向けの病理学の本が少ない中で、これほどコンパクトにわかりやすくまとめられた本は貴重でしょう。 自身の体を知るための一冊として、病理学の超・入門書の本書を皆さんも読んでみてはいかがでしょうか? 本書の終わりでは、「からだのことをもっと知るためのブックガイド」として、仲野さんによるおすすめ書籍も紹介されているので、これを機にさらに知識を深めるのもおすすめです。